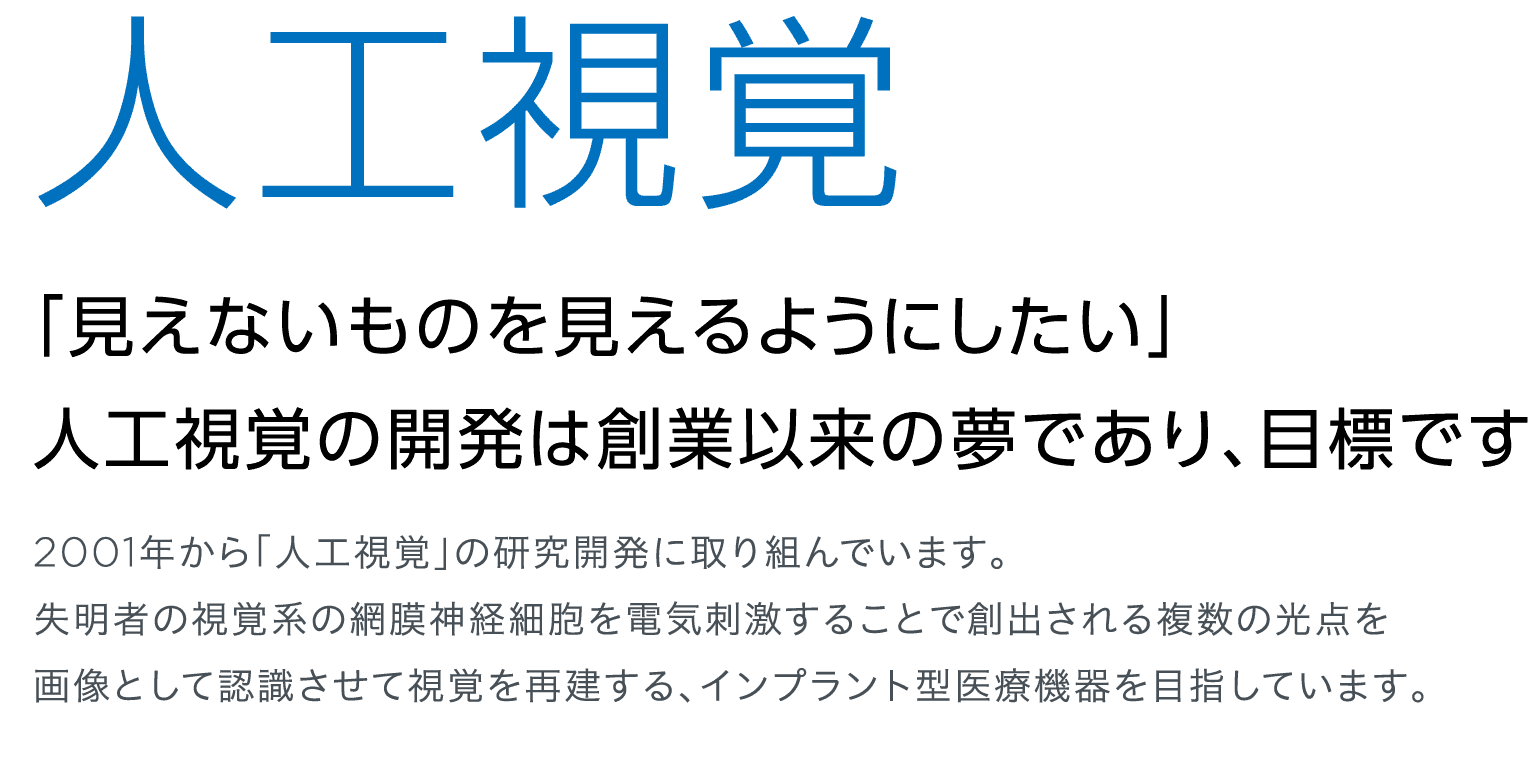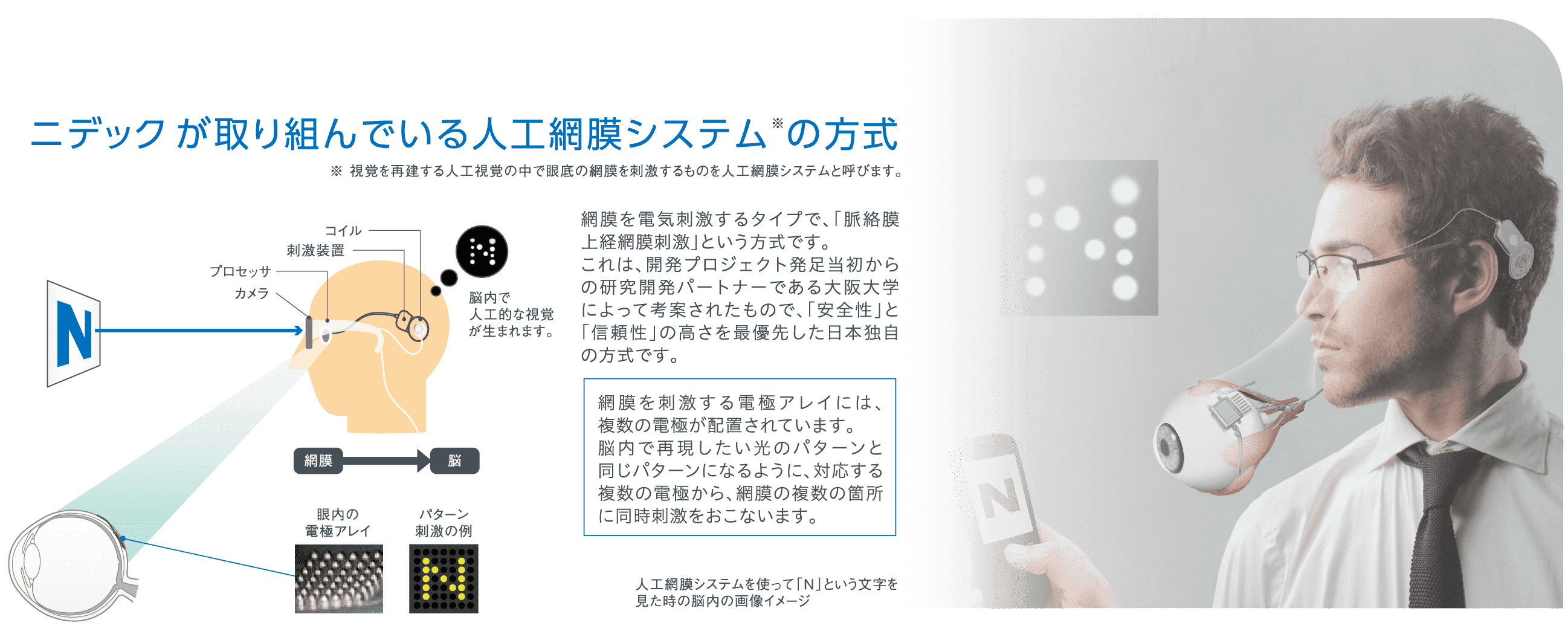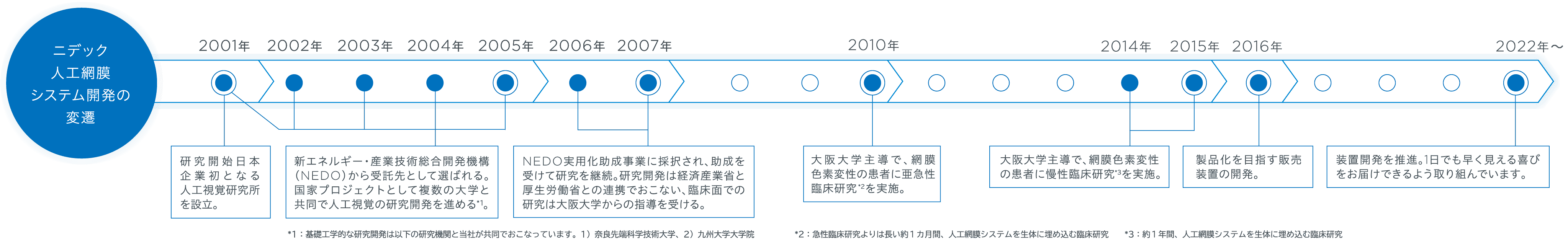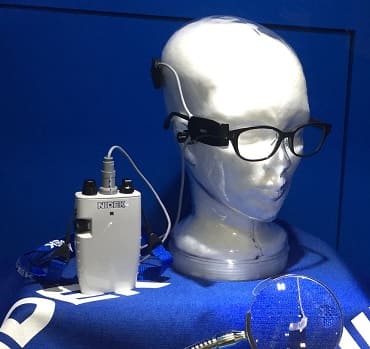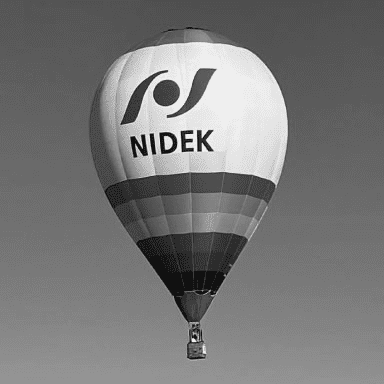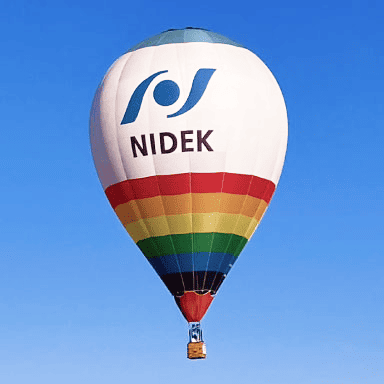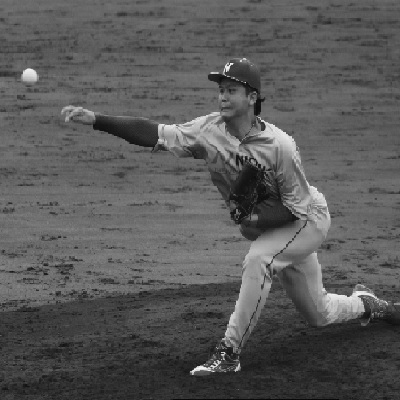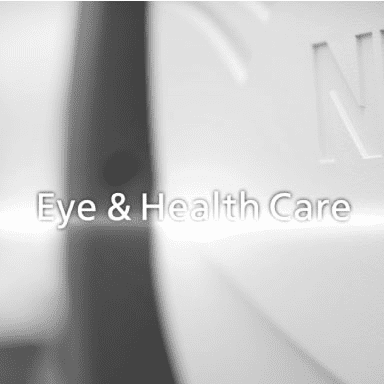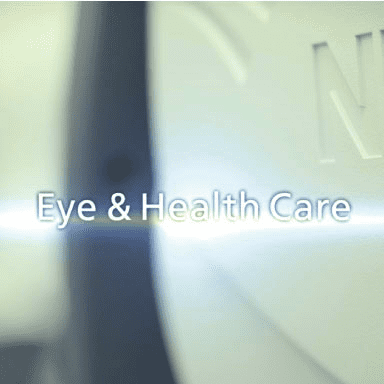- TOP
- ニュース / イベント
- 企業情報
- 事業紹介
- サステナビリティ
- 採用情報
光凝固装置
白内障/硝子体手術装置
眼内レンズシリーズ
光凝固装置
涙道チューブ
屈折度測定装置/角膜曲率半径測定装置/眼圧測定装置
角膜内皮細胞撮影装置
PDメータ
角膜形状/屈折力解析装置
光干渉式眼軸長測定装置
超音波診断/測定装置
累進マークチェッカー
網膜観察装置
眼底カメラ
ゴニオスコープ
光干渉式眼軸長測定装置
超音波診断/測定装置
スリットランプ
診療所向け電子カルテシステム
自家培養角膜上皮
自家培養口腔粘膜上皮
眼底カメラ
光干渉断層計(OCT)
視力計
レンズメーター
屈折度測定装置/角膜曲率半径測定装置
累進マークチェッカー
PDメータ
レンズ加工機
コーティングサービス
ハードコート製品
一般向け製品








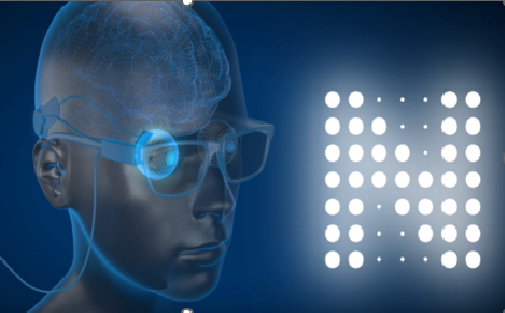





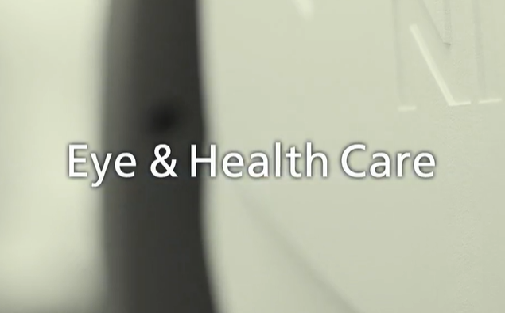
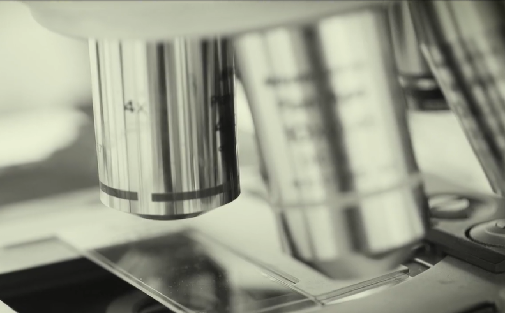

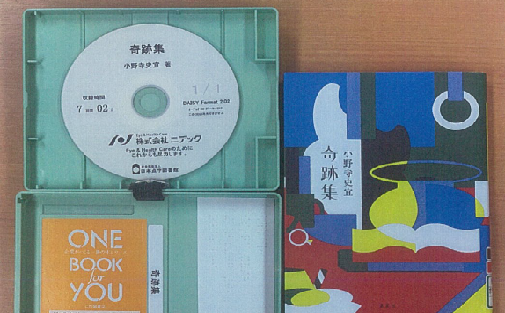

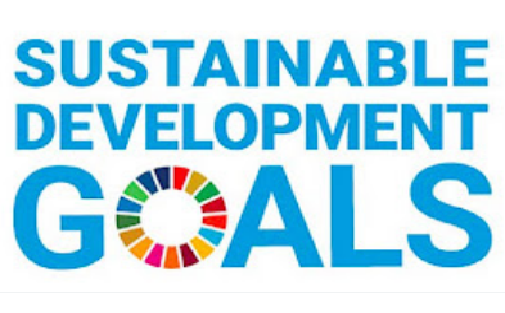

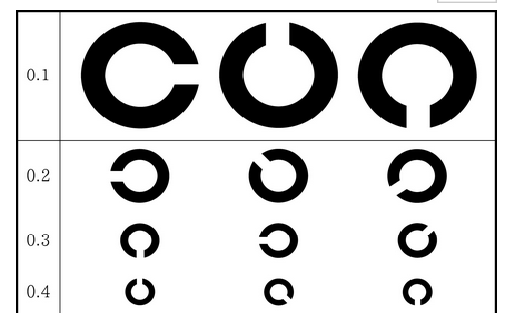








 TOP
TOP